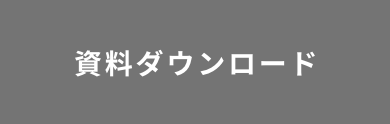- 特定技能
続報 育成就労の運用に向けた有識者懇談会が開催!在留資格認定や転籍はどうなるのか?解説

目次
令和6年6月14日、第213回通常国会において、人材育成と人材確保を目的とする育成就労制度の創設等を内容とする法律が成立し、令和6年6月21日に公布されました。
令和6年入管法等改正法について|出入国在留管理庁
令和7年3月に有識者懇談会が開催されましたので最新の検討状況を解説いたします。
施行までのスケジュール
育成就労制度については、改正法の公布日(令和6年6月21日)から起算して3年以内に施行されます。
具体的な施行日は現時点では引き続き未定です。
また、既に現在受け入れている技能実習生については、引き続き認定計画に基づいて技能実習を続けることができます。
今後、技能実習生の受け入れを検討している場合、改正法の施行日までに技能実習計画の申請を行い、原則、施行日から3か月を経過するまでは技能実習を開始できます。
ただし、技能実習1号は技能実習2号への移行もできますが、技能実習3号への移行については改正法施行日以降は一定の範囲に限られます。
新たな在留資格「企業内転勤2号」
現行の技能実習制度において、外国の支店や子会社の社員等を短期間、企業単独型の1号技能実習で受け入れているようなものについては、一定の要件の下、新たに創設される在留資格「企業内転勤2号」により受け入れることを想定しています。
「企業内転勤」とは、外国の支店など事業所から日本の事業所に一定期間、転勤する外国人のための在留資格です。
企業内転勤ビザでは「技術・人文知識・国際業務」ビザに当てはまる仕事内容で就労が認められており、転勤期間は限定されています。
これまでの企業内転勤ビザでは、研修や修行を目的とした就労が不可でしたが、企業内転勤2号では一定期間、基準を満たしていれば研修を目的とした就労が可能になります。
育成就労計画の認定基準について
従事できる業務範囲を拡張し、特定技能の業務区分と同一としつつ、特定技能1号の技能水準への人材育成が計画的に行われるための検討がされました。旧制度の「必須業務」「関連業務」「周辺業務」「安全衛生業務」の規制や取り扱いについては、①育成就労においても技能の習得に必要な「必須業務」は継続して設定し、②「関連業務」「周辺業務」の区分は撤廃しつつ、「必須業務」については、育成就労の期間の3分の1以上従事することを要件とすることが良いのではないかとされています。これは旧制度の2分の1以上から、より育成に重点を置いた基準に変更されるものと考えられます。
旧制度(技能実習制度)からの移行措置について
技能実習中に新制度が施行された場合、施行日時点で実習2号を1年以上実施している場合は実習2号終了後に実習3号に移行することを認める方向性が示されました。これにより、技能実習生や受け入れ企業が無理なく新制度に移行できるよう配慮されています。また、技能実習2号を良好に修了した者については、施行後も一定期間は試験免除で特定技能1号への移行を引き続き認めることを検討しています。これは、技能実習制度からの移行を円滑に行うための措置だと考えられます。 さらに、育成就労期間のイレギュラーな事案の取り扱いについては、妊娠・出産等による中断・再開は旧制度同様認められます。また、季節性のある分野(農業・漁業)に限り、業務の存在しない一定の期間(6ヶ月未満)の一時帰国を認め、帰国期間を除いた通算3年間の育成就労を実施することとしています。一時帰国・再入国に係る旅費は、育成就労実施者または監理支援機関の負担とするとのことです。 試験不合格時の取り扱いについては、適正な育成就労を行っていたにもかかわらず目標に定めた試験に合格できなかった場合や、やむを得ない事情により試験を受験できなかった場合に、同一の育成就労実施者の下で継続する場合に限り、目標とする試験日程に必要な範囲で期間延長の申請が可能とされています。
育成就労制度での転籍
育成就労制度においては、人権侵害を受けた場合等「やむを得ない事情」がある場合の転籍を認めるほか、一定の要件の下、本人の意向による転籍も認めることとしています。
一定の要件としては、
(1)転籍先の育成就労実施者の下で従事する業務が転籍元の育成就労実施者の下で従事していた業務と同一の業務区分であること
(2)転籍元の育成就労実施者の下で業務に従事していた期間が、育成就労産業分野ごとに1年以上2年以下の範囲内で定められる所定の期間を超えていること
(3)育成就労外国人の技能及び日本語能力が一定水準以上であること
(4)転籍先の育成就労実施者が適切と認められる一定の要件に適合していること
などがあり、その詳細については、今後具体化していく予定としており確定はしていません。以下で検討されていることを解説します。
本人意向による転籍の要件について
受け入れ機関は、紹介費・送出手数料・入国後講習費などの初期費用を負担して受け入れ 、本人意向による転籍の場合、転籍後の受け入れ機関が初期費用の一部を分担する仕組みを検討しています。転籍元・先が補填する初期費用額の交渉が理由で転籍の妨げとなることを防ぐルールを以下のようにしています。
①職業紹介費・入国前後の講習費・来日渡航費等が初期費用にあたることとし、 その総額を一律の標準(固定)額として評価する
※来日渡航費及び送出管理費の一部に限っては、実費を勘定して初期費用に含める
②転籍先が補填すべき初期費用について、在籍期間に応じて按分することとする
→外国人の生産性向上に鑑み、例えば、按分割合を一律 1年目:2年目:3年目=1:2:3と傾斜をつけて設定
※ この場合、転籍先は、1年で転籍した場合には初期費用の5/6を、 2年で転籍した場合には3/6=1/2を補填することになる
その上でこのように計算された補填額を、転籍先が転籍元に支払うことを約束すれば転籍可能とするとしています。
就労前の日本語要件
育成就労制度では、入国時に技能の要件はありませんが、日本語要件が新たに設けられる予定です。
日本語能力A1相当以上の試験(日本語能力試験N5等)の合格又はこれに相当する認定日本語教育機関等による日本語講習の受講が求められます。
なお、必要となる日本語能力レベルについては、産業分野ごとにより高い水準とすることも可能となる予定です。
A1レベルの日本語とは?
具体的な欲求を満足させるための、よく使われる日常的表現と基本的な言い回しは理解し、用いることもできる。もし、相手がゆっくり、はっきりと話して、助け船を出してくれるなら簡単なやり取りをすることができるレベル、とされています。
参考までに日本語能力試験はN5相当とされており、就労場面では顧客等とのやりとりはせず上司・同僚から簡単な指示を受けて行う単独業務が想定されます。
まとめ
今回の議論でもまだ確定はせず、検討の段階であるとしていました。育成就労制度は、2027年の施行開始を目指していますが、今後の方針が変更される可能性はまだまだ十分にあります。外国人材の採用を検討している企業にとっては、今後の情報に細心の注意を払うことが重要です。市場の動向や法令の改正に関する最新情報を把握することで、適切な対応が可能になります。したがって、関係者は定期的に情報収集を行い、変化に柔軟に対応できる体制を整えることが求められるでしょう。
育成就労制度の概要はこちら→https://www.moj.go.jp/isa/content/001421922.pdf
育成就労制度・特定技能制度Q&Aはこちら→https://www.moj.go.jp/isa/applications/faq/ikusei_qa_00002.html
育成就労制度を含む改正入管法については、随時詳細が発表されていくものとみられます。
弊社では最新情報をお届けしております。ご不明な点がございましたら是非お問い合わせください。